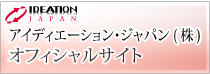TRIZの古典
アルトシューラ「発明的創造の心理学について」
この論文は The Official G.Altshuller foundation の許可に基づいて掲載されたものです。 (下記のURLはファウンデーションのサイトにリンクされています。書誌詳細はページ末尾)
This paper was published with the permission of the Official G.Altshuller foundation: www.altshuller.ru/world/eng/index.asp.
この論文の著作権は The Official G.Altshuller foundation にあります。
日本語の翻訳の著作権はサイト管理者にあります。
無断転載は禁止いたします。
発明的創造の心理学について
労働手段の改良をおこなう時の人間の心理の研究は、技術革新の基盤である技術分野における人の創造的活動にみられる法則性の解明と理解にとって重要な意味を持っている。
技術分野の創造活動の重要性と、これまで心理学においてこの問題に向けられてきた関心との間には、残念ながら明らかな落差がある。この落差の大きさを知るには、1934年に出版されたP.M.ヤコブソンの著書『発明における創造的活動のプロセス』が、ソビエトの心理学文献におけるこの問題に関する唯一のモノグラフであると指摘することで十分であろう [7]。P.M.ヤコブソンの著書は、著者が拠り所とする命題が誤っているにもかかわらず、他に研究が存在しないために、一般心理学の教科書、研究作業の組織化に関するモノグラフ、さらには一般向け科学書に書かれた創造的活動に携わる技術者の心理についての記述に多大の影響を与えてきたし、また現在も与え続けている。
ヤコブソンの著作はD.ロスマン [8] が提唱した、創造的プロセスを形式的・経時的に複数の段階に区分する方式に基づいたものである。
D.ロスマンとP.M.ヤコブソンは、発明者の創造的活動に内在する法則性を研究せず、他方で、解決策を探求する段階と、それを技術的に具現化する段階という、心理学的特性からみて相互に異なる2つのプロセスを同一視する。これはD.ロスマンも、またP.M.ヤコブソンも、技術的創造全般、特に発明における創造という心的活動の特性を明らかにすることができなかったためである。その結果、技術革新の心理学に関する原則的な問題が未解決のまま残されることになった。両者は、この問題に研究のメスを入れることなく「ひらめき」、「見えてくる」、「推測」、「アイデアの芽」、「アイデアを育てる」などといった、具体的な科学的内容を欠いた用語を使っている。
K.G.ヴォブルイのモノグラフ「科学研究者の労働の組織化」の中の関係する各章もこれと同じ誤った立場から書かれている。K.G.ヴォブルイは「創造的プロセスの前段階として、準備、アイデアの育成、アイデアの熟成、ならびにひらめきという諸段階を認めることができる。日常的思考の流れの中では、これらの段階はしばしば重なり合っている」
と書いている [2; 123〜124]。この「分析」が、それより50年以上も前にT.リボーによって述べられていた見解、すなわち「この潜在的活動が十分な段階まで進んだ時に、意識的な知的緊張の結果として、あるいはまた、何らかの気づきによって、あたかも然るべき解決策を隠していた幕がさっと上がったかのように、解決のアイディアが突然姿を現す」[5; 228]
という所説からいささかも前進していないのは興味深いことである。
これらの見解の基礎には、A.ベンによって提唱された技術分野における創造活動の様々なプロセスのあらゆる多様性を「試行錯誤の法則」に基づく「思考実験」へと帰着させる「建設的知性」の理論が横たわっている。この理論の影響は、S.L.ルビンシュテインの「一般心理学概論」のようなきわめて重要な労作にさえ現れている。「合理化、修正、あるいは何らかの新規性を求める点が発見され、着目され、認識され、発明者の意識の中に深く根づいた時に、発明者の頭脳に浮かんでくるきわめて多様な観察所見やありとあらゆる知識のこの一点への集結と吸収という特異な過程が始まる。これらすべての観察所見と諸事実は、あたかもこの中心に向けて狙いを定めたかのように集結し、発明者の思考をとらえている課題と関連づけられる。そして、発明者の頭の中に時としてまったく予期しなかったような組み合わせが多数生じてくる。」[6; 576]
しかしS.L.ルビンシュテインは、一方では技術分野における創造活動の特性を初めて次のように正しく指摘している。「発明は、特定の問題を解決することのできる物、実在する事物、メカニズム、方法を創出しなければならないという特性によって、他のタイプの創造活動と区別される。発明者の創造活動はこれによって規定される。すなわち、発明者は、現実のコンテキスト、何らかの活動の実際の流れの中に新しいものを導入しなければならない。それは、抽象的に取り出された限られた数の条件を考慮すべき理論的問題の解決とは本質的に異なるものである。発明者にとって、現実とは、人間の活動と技術とによって歴史的に媒介された現実であって、ここには科学的思考の歴史的発展が体現されている。それ故、発明の過程は、何らかの新規性を導入すべき現実のコンテキストから出発し、また、これに対応する科学的コンテキストを考慮しなければならない。発明のプロセスを構成する様々な要素の持つ一般的方向性および固有の特質はこれによって規定されている。」[6; 575]
しかし、この定義は完全に正確という訳ではない。なぜなら、例えば建築家もまた「実在する事物」を創出し何らかの新しいものを「現実的コンテキスト」のうちに導入し、かつこの際に「これに対応する科学的コンテキスト」を考慮しなければならないからである。この不正確さのため彼のきわめて多産で重要な思想が事実上見過ごされてしまい、広く普及している学校教科書では今日でも単に創造「一般」についてしか語られないことになってしまった。
創造に関する心理学は、心理学の中で研究が最も手薄な分野の1つとなっている。
創造は、複雑なプロセスであり、そこに内在する法則性は多様で捕らえ難い。しかし、発明という創造活動が持つ特殊性がこのプロセスの研究者にとっての課題をある程度まで容易にしている。芸術における創造の結果は、芸術作品が反映する客観的現実だけでなく作者の世界観や美的理想さらには偶然的要素など多数の要因に依存している。これに対して、技術分野の創造活動の方は一定の法則に従って発展する技術の変化と結びつけられている。新たな労働手段の創出は、それに対する主観的態度とはかかわりなく、客観的法則性に従がわざる得ない。一般的に言えば、芸術における形象化は、多くの点で(例えば物語、伝説、神話におけるように)現実から遊離したものであり得る。しかし、あらゆる技術的課題は科学的法則に従い、技術発展の法則性に依拠しなければ解決することはできない。
発明的創造の心理学の研究は、技術の進化に関する基本法則の研究と切り離して進めることはできない。発明者の活動は新たな技術的事物の創出に向けられており、発明者は技術進歩の過程への参加者の一人である。それ故、発明的創造の心理は、技術の進化に関する法則についての深い知識があってはじめて理解可能となる。言うまでもなく、今述べたことは、この研究が技術進歩のメカニズムの研究に限定されるということを意味しない。科学の一部門としての発明的創造の心理学の独自性は、技術発展の客観的法則性と主観的・心理的要因とを同時に考慮しなければならないという点にある。発明的創造の心理学は、何よりもまず、心理学の一分野である。それ故、その関心の中心には、発明者たる人間、すなわち技術の改良や開発に従事する人間の精神活動がある。発明的創造の心理学は、人間心理の主観的世界と技術の客観的世界との間をつなぐ架け橋の役割を果たすものであり、だからこそ、発明的創造の研究に際しては技術の進化における法則性を考慮に入れなければならないのである。
発明における創造プロセスは、物質的・事物的側面と心理的側面の2つの側面をもっている。発明活動の物質的・事物的側面を解明するためには、技術発展の歴史に関する知識と技術進化の基本法則に関する理解が必要とされる。技術史に関する資料の研究と具体的発明の分析が技術的創造の心理学の最も重要な源泉の1つをなしている。
発明活動の心理的側面における法則性を解明するためには、技術者の創造プロセスの体系的観察、技術者の経験の一般化、ならびに現実に最大限近似させた条件におけるテストによる発明の際の創造プロセスの実験的研究が必要とされる。
筆者等は1948年からこの方針による作業を行なってきた。多数の技術史資料や著名な発明家の仕事に関連する幅広い回想文献を調査し、「ソ連発明集成」に記載されている発明の説明および諸外国の特許文献の体系的研究を行った。ソ連産業界の先進的企業の革新的技術者の経験を分析して、そこに一般的傾向を発見することに特別な注意が払われた。我々自身で行ったアゼルバイジャン石油産業における開発、改良に携わる技術者の創造的活動の観察結果が活用された。これらの作業を通じて得られた結果についてヴァノ・スツルア記念クラッキング工場および「レーニンネフチ」油田管理所の第8企業体の2箇所の機械生産工場で実地検証を行った。
このようにして得られた結論を正確に説明するためには技術進化の基本法則の内容を紹介する必要がある。この法則の体系は複雑かつ多様であり、これを紹介することは本論文の課題ではないので、ここでは創造的プロセスの本質を理解する上で不可欠な情報を紹介するにとどめたい。
K.マルクスは「資本論」において、機械の構造・機能的特性を次のように特徴づけている。「あらゆる発達した機械の総体 (entwickelte Maschinerie) は、本質的に異なる3つの部分、すなわち、原動装置、伝動機構、および道具機構あるいは作業装置から成っている。原動装置は全装置の原動力として働く。原動装置は、蒸気機関、熱機関、電磁気機関などのように、それ自身で原動力を生み出すこともあれば、また、水車が落水から、風車小屋の風車が風からというように、外部の何らかの既存の自然力から作用を受け取る場合もある。伝動機構は、運動を調節し、必要があれば運動の形態を、例えば垂直運動から円運動にというように変化させ、それを分配して作業装置に伝達する。装置の中のこの2つの部分は、作業装置を運動させ、これによって作業装置が作業対象を目的に応じて変化させるようにするためにのみ存在する。」[1; 378〜379]
機械の主要構成要素である作業装置、伝動機構および原動装置の間には一定の相関関係がある。なぜなら、これらすべての部分は密接な相互連関と相互被制約性のうちにあるからである。生物学者の間ではダーウィンが成長の相関法則と名づけた法則(生物体の各部分の変化は、常に他の部分の変化と相関関係にある)が古くから知られている。この法則は、現象の普遍的相互連関についてのマルクス主義弁証法の有名な命題の特殊例である。機械の進化の過程での各構成要素間の相互被制約性は同じ一般法則のもう1つの特殊例といえる。
機械の主要構成要素の間に相互連関が存在することの結果として、個々の要素の進化には限界があることになる。即ち、個別要素は進化によって変化する部分と変化せずに残った他の部分との間で矛盾が発生しないという限界の範囲内でのみ進化することが可能である。そこで例えば、単に「作業装置の寸法および同時に作動するツールの数が増えるだけでも、より大きな原動装置が必要となる……。17世紀に1つの水車で2つの回転石と2つのひき臼とを同時に動かそうと試みた際に、伝動装置の寸法を大きくすると水力が足りなくなってしまうという矛盾が発生した……」[1; 382〜383]
。機械の構成要素同士の間に発生する矛盾は機械全体の進化にブレーキをかける。というのは、相互に矛盾を抱えたすべての要素を変化させ、その特性を根本的に改善しない限り機械全体をそれ以上改良することは不可能だからである
自転車の歴史から主なできごとを取り出してみよう。オーストリアの営林署長ドライスが現在の自転車の原型である「駆け足機」を製作したのは1813年のことだった。ロシアの優秀な機械技師であるL.シャムシュレンコフとI.N.クルビンによって設計された自走四輪車は、西ヨーロッパでは知られていなかった。そのため、ドライスによる最初の自転車にはロシアの発明家の四輪車が備えていたあるもの、すなわちトランスミッションがなく、走行する時は両足で地面を蹴らなければならなかった。この自転車には伝動機構が欠けているため作業装置(車輪)や操縦装置をさらに改良することは何ら意味をもたなかった。このため「駆け足機」は移動手段ではなく遊具となってしまった。前輪の軸に取り付けるペダルが導入されてはじめて自転車が改良される可能性が生まれた。ペダルによって走行速度を増加させることが可能になったが、しかし速度の増加に伴い制御装置の欠陥に起因する走行の危険性も増大した。この障害はブレーキの発明(1845年)によって取り除かれた。その結果、駆動輪の直径を大きくしこれによりペダル1回転による自転車の進行距離を増大させる形で、作業装置をさらに進化させることが可能となった。前輪の直径は年毎に増加してゆき、巨大な前輪を備えた「クモ」と呼ばれる自転車が出現した。こうして進化を量的に実現する考え方が可能性の限界に達してしまった。駆動輪の直径をこれ以上増加させると走行時の危険が極度に高くなるからである。この矛盾は伝動装置の変更(チェーン伝動の採用)によって解消された。チェーン伝動により車輪の直径の大きさではなくて、足踏み回転数を増加させる方法で高速を得ることができるようになった。伝動装置の改良は作業装置の進化のための新天地を再び切り開いた。空気入りタイヤが導入されたのは1890年のことである。これによって走行速度が増大したため、伝動装置がさらに改良(フリーホイール機構の採用)されることになった。今日の自転車は、このようにして生まれたのである。
自転車の発達をごく駆け足で概観しただけでも、次のような帰結を得ることができる。
- 装置、機構、工程の個々の要素の間は、常に密接な相互連関がある。
- 進化は不均等に生じ、一部の要素がその発展の過程で他の遅れた要素を追い越す。
- システム(装置、機構、工程)を計画的に進化させることが可能なのは、進んだ要素と遅れた要素との間に矛盾が発生し、それが激化するまでに限られる。
- 矛盾は、システム全体の進化を引き止めるブレーキとなる。発生した矛盾を取り除くことこそが発明である。
- システムの一部分を根本的に変更すると、その変更が必然的に求める条件に従って他の部分に一連の変更を加える必要性が生じる。
したがって、新しい技術的課題が革新的方法で解決されたとすれば、課題がどの技術分野に属するかにかかわりなく、そこには次の3つの基本的要素が含まれていなければならない。
- 課題を設定し当該の技術分野で知られた通常の方法で課題を解決することを妨げている矛盾を明らかにすること
- 新しい従来より高い技術的効果を得るために矛盾の原因を取り除くこと
- 改良対象システムの構成要素のなかで[矛盾の除去に伴って]変化した要素に合わせて他の諸要素の最適化を実現すること(システムが新しい性能に適した新しい形を得る)
これに対応して、新しい技術的課題を創造的に解決するプロセスには通常それぞれ目的と方法の異なる3つの段階が含まれることになる。これらを暫定的に、分析段階、操作段階および総合段階と呼ぶことにする。
分析段階の目的は、当該の装置、機構、工程(またはより幅広く、技術分野)の進化の状況を分析することにある。これは現在の発展段階における主要な矛盾を明らかにし、この矛盾の直接の原因(物理的、化学的原因等)を特定するためである。操作段階とは、こうして特定された矛盾の原因を取り除く方法を体系的かつ合理的に検討することにほかならない。総合段階は、前の段階で発見された技術的な矛盾の原因を取り除く方法に対応して、システムのその他の諸要素を変更することに向けられる。
(分析段階)
研究者の創造的活動は分析段階の第1ステップすなわち課題の選択から既に始まる。発明者は「変化、作り替え、改良が可能」なのは何かを注意深く観察する心構えを育まなければならないというS.L.ルビンシュテインの意見は完全に誤っている。すべてのツール、技術装置は例外無く変化させ改良することが可能であり、変更され得ないものは存在しない。研究者の課題は、たまたま視野に入ってきたテーマを機械的に選択することではなく、特定のシステムの進化のダイナミックスを創造的見地から研究し、そのシステムの全般的進化に対するブレーキとなっている現段階での制約的な問題を発見することにある。
このことは、計画生産と結びついているソ連の発明活動の場合に特に典型的な形で現れている。現代の生産活動、とりわけ最終製品の生産活動は、相互に関連した多数の工程から成り立っている。企業の総生産能力は、通常これらの工程のうちの一部、すなわち生産活動全体の中の「ボトルネック」によって制約されている。もし発明者が無計画に「変化、作り替え、改良が可能」なものすべてに取り組めば、生産工程の幾つかでは生産能力に余裕が生じるが、全般的な進化が「ボトルネック」によって引き止められているため、せっかくの余裕が活かされることはないのである。
バクー金属製石油容器工場の技術開発および企画部門の経験は、きわめて興味深い。この工場における生産プロセスは、すべての部門が足並みをそろえて作業をすすめることを必要としている。ここでの生産合理化活動は、部門ごとに担当技術者によって個別に進められていた。この体制下では、多数の新機軸が導入されたにもかかわらず、工場の総生産能力はほとんど増加しなかった。例えば、溶接部門の生産技術者が自動溶接機を大きく改良した。これによって溶接工程をスピードアップすることが可能となった。溶接機の稼動時間当たりではより多くの製品が生産されるようになった。しかし同時に、溶接機の休止時間も増加した。この休止は前処理部門の生産性が従来と変わらなかったことに起因していた。このような経験に基づいて1948年初めに、生産全体の向上を遅らせている「ボトルネック」を発見する目的で工場内の体系的な調査が行われた。これによって最も緊急を要する課題を特定することが可能となり、それ以降、技術開発および企画部門の力は、こうして特定された課題を計画的に順次解決することに向けられるようになった。その結果、1948年から1955年までの期間に工場の労働生産性は8倍増加した。
分析段階の第2ステップは課題中の最大の重点の抽出である。個々の具体的技術課題の解決に当たっては、あらゆる装置、機構、工程について、求められる技術的アウトプットを実現するためには、どの特性(構成要素)を変更することが必要で十分なのか、その要点となっている特性(構成要素)を選び出さなければならない。
英国の著名な発明家ジェームス・ワットによる技術革新は、最重点課題を的確に抽出した古典的なケースといえよう。ワットは蒸気機関の改良を自分の課題として、当時存在した蒸気機関のすべての特性を詳細に分析した。当時の蒸気機関には、ボイラーの寸法が巨大でかつ爆発の危険があること、シリンダーで膨大な熱が失われていること、動力伝導装置の欠陥など、多数の重大な欠点があった。この中から、ワットがシリンダー内の熱損失の低減、したがってまた機関の全般的効率の向上を課題の最重点として取りあげたことは適切だった。ワットの功績によりこの特性が改善されたことによって、十分に高い出力を備えた蒸気機関を作ることが可能となった。ワットはさらに、蒸気機関を汎用化するという新たな課題を設定した。これまでの改良によって蒸気機関は当時の社会で必要とされる出力を備えるようになっていた。他方で、蒸気機関がつくり出す運動は実際上めったに利用されない往復運動である。そこで、汎用化の最重点は伝動機構の改良となった。ワットは課題の重点をこのように移し、往復運動を円運動に転換する伝動機構を作ることで、蒸気機関に求められる汎用性を実現することができた。
課題の選定およびその最重点の特定は、技術的創造プロセスの(第一段階である)分析段階の前半をなすにすぎない。こうして特定した課題を既知の技術的手段で解決しようとすると、求める効果を得ることを妨げる矛盾が発生する。こうして、進化を制約している矛盾を発見することが分析段階の第3ステップとなる。
例えば、熱スクリーンや熱交換器を追加してボイラーの効率を改善しようと試みると、装置が重くなり製作に要する金属材料の量が増加する。このように、通常の手法によって特性の1つを改善しようとすると、同時に他の特性を悪化させてしまうことになる。「重量を削減しようとすること(材料の節約)と、効率を向上させようとすること(燃料の節約)とは、ある面で相互に矛盾する。この矛盾の解決が、ボイラーの進歩にとって最も重要な要因の1つとなっている。」[4; 146]
矛盾の発生は、何らかの原因によるものであろう。したがって、矛盾の直接の原因(機械的、化学的原因等)を確定することが、技術的創造プロセスの分析段階の最終ステップ(第4ステップ)となる。実例をあげてみよう。目盛板式計測器製造の最終段階は、基準器との対比による検査である。計測器は基準器と並べて置かれ、検査係がいくつかの目盛点で表示が一致するか否かを検査する。言うまでもなく、検査の精度を向上させるためには出来るだけ多数の目盛点で検査を行う必要があるが、これを行うと検査に要する時間が長くなり、検査係の労働生産性が低下してしまう。精度の面で改善しようとすれば、検査時間が延長されることになってしまう訳である。この矛盾の直接の原因は2台の計測器の目盛を一カ所に重ねることが物理的に不可能なことである。検査係は片方の計測器からもう一方の計測器に視線を移さざるを得ない、しかし、必要なのは両方を同時に見ることである。とすれば、双眼鏡のような仕組みを使って2台の計測器の目盛板を光学的に重ね合わせ、2台の示度の重なりを目盛全体にわたって迅速かつ正確に検査できるようにすれば矛盾は解決される。
分析段階は技術的創造プロセスの諸段階の中で最も「論理的」な部分である。経験豊かな技術者にとってこの段階は、歴史的、統計的、技術的、経済的その他の事実に基づいて様々な判断を論理的に積み上げる段階である。分析段階のいずれかのステップで事実データが不十分なことが判明し、目的に合わせて実験を行うことが必要となるのはまれなケースに限られる。
同時に、分析段階は技術的創造プロセスの中できわめて重要な部分である。多くの場合、分析を正確に行うことによって技術的矛盾の原因を即座に取り除く除こと、あるいは次の段階(操作段階)の作業を極めて容易にすることが可能となる。
分析段階を成功させる上での要件は何だろうか。それは、研究の対象とする技術分野の深い知識を持っていること、技術進化の弁証法的法則を理解していること、分析に必要なあらゆる事実データを保有していること、そして論理的分析を進める技能である。したがって、発明する能力を高めるには、分析スキルを恒常的に訓練することが必要である。外科医は生きている人間の手術をするまでに、解剖学教室で長時間訓練を受ける。それとまったく同じように、新技術を開発できるようになるには過去の発明を体系的に分析しなければならない。技術史の知識、つまり各技術部門をその変遷と進化の流れの中で理解する能力もまた重要である。最後に、技術的知識の量そのものや手持ちの事実データの量も重要である。
(操作段階)
技術的創造のプロセスの第2の部分操作段階は多くの点で最初の部分(分析段階)と異なっている。操作段階は、多くの場合、論理的作業と非論理的作業とが組み合わされたものとなる。この段階で技術者は探索し、試行し、あるいはあまり正確でない古い用語を使えば「思考実験」をしなければならない。ここで強調しておく必要があるのは、技術的創造プロセスの中で「思考実験」が主要な役割を占めるのは操作段階のみであるという点である。また重要なのは、「思考実験」は決してランダムに行われるわけではないという点である。仮に「思考実験」が「きわめて多様な観察所見やありとあらゆる知識のこの一点への集結と吸収という過程」(S.L.ルビンシュテイン)
であるとすれば、どのような具体的な技術課題であってもそれを革新的なやりかたで解決するには何年もの歳月が必要となってしまうだろう。多少なりとも経験を積んだ技術者は誰でも技術的創造プロセスの操作段階の作業を計画的に進めている。技術者は、往々にして自分でも完全には自覚していないものの長期の実践を通じて徐々に、客観的に見て合理的な自分なりの探索システムを形成しているものである。前述の分析段階の作業はこの探索作業を多くの点で容易にしてくれる。なんとなれば、技術者は操作段階で抽象的な「アイデア」を探索するのではなく(分析段階で明らかにされた)具体的な技術的矛盾を具体的に取り除く方法を探索することになるからである。
我々の見解によれば、この段階における最も合理的な作業プロセスとは、技術的矛盾の原因を取り除く方法を次の順序で探索するものである。
- 典型的解決法(モデル)の研究
- 自然的(自然の中に存在する)モデルの応用
- 他の技術分野のモデルの応用
- 解決策をもたらす新しい方法を、次の各部分を変更する観点から発見しようとする探索
- システムの範囲内における変更
- 外部環境における変更
- 隣接システムにおける変更
この順に従えば考察は単純なものから順次複雑なものへと進むので、最小限の労力と時間とで正しい解決を得ることが可能となる。
創造活動のプロセスで遭遇する技術的矛盾は、自然や既存の技術の中に直接的なアナロジーをもっている場合が多い。それ故、自然や既存の技術の中に存在する類似した矛盾とその典型的な除去法を最初に研究することが合理的といえる。この研究を通じて技術的矛盾の原因を取り除くために自然または既存技術に存在するモデルを応用できる例は少なくない。
実例をあげてみよう。第一次世界大戦中に艦船で水中ソナー(潜水艦のスクリュー音を聴取するための装置)を使用するようになった。しかし当初は、艦船を停止するか航行速度を極端に遅くしないとソナーを使用することはできなかった。ソナーが引っ張られることでソナーの周囲に発生する乱流の雑音でそれ以外の音が全て消されてしまうからである。ソナーの改良を担当した技術者の中にアザラシは水中を最高速度で泳ぎながら音を聴くことができることを知っている者がいた。この技術者の提案に従ってソナーの受信部をアザラシの耳殻に似た形状とすることにした結果ソナーの感度が大きく改善されて艦船が航行中でも使えるようになった。
1933年にソ連で飛行機からパラシュートなしで貨物を投下する装置(発明者証番号41356)が発明された。この装置を設計した技術者は広く知られているカエデの種子の特徴を応用した。カエデの種子は回転運動をしながら水平にゆっくりと滑空する。この考えに沿ってカエデの種の形状を模して設計された装置は飛行機から投下されると重心を中心として回転しながら、ゆっくりと降下する。
技術的モデルを応用した典型的な例は、深層用ポンプのバルブの耐摩耗性を改善した設計技術者E.V.コストイチェンコ(機械製作工場)の発明である。油井から石油を採取するのに使われる深層用ポンプは、石油に含まれる砂によってバルブが摩耗して短時間で故障する問題があった。硬合金を使用してバルブの寿命を向上させることを試みたが好ましい結果が得られなかった。なるほどバルブの耐久性は向上するのだが、一方で、バルブの加工と組み立てが非常に複雑になり、製造コストが上昇してしまうのである。E.V.コストイチェンコはこの矛盾を取り除くために、機械産業の別の分野で知られている方法を応用した。工作機械分野で使われているセルフシャープニング式バイトは表面の何層かが比較的硬度の低い材料で作られている。これらの層は使用中に均等に擦り減ってゆくため、カッティングエッジ全体の形状が保たれる。これにヒントを得て、深層用ポンプのバルブの部品の一部に硬度の低い鋼材を用いることで、バルブの摩耗が均等に進むようにすることに成功した。その結果、摩耗部の部品が新品の9割分摩滅しても、バルブの形状が保たれるようになった。現在、多数の石油掘削現場でE.V.コストイチェンコのバルブをつけたポンプが10万台以上稼動している。
自然あるいは既存技術に存在するモデルの応用は、言うまでもなく、単なる模倣に限定されない。こうしたモデルは長期間継続してきた進化の結果である。技術者は自然や技術から借用したモデルをさらに発展させ、その論理的帰結に至るまでに仕上げなくてはならない。
自然や既存技術に存在するモデルの研究が好結果につながらない場合には、操作段階の次のステップである(モデルの無い)新たな方法の探求に移ることになる。この場合、まず最初に検討すべきなのはシステム自体の内部をどのように変化させることが可能かということである。これは変化させ方が最も単純な通常のグループと見なすことができる。技術的矛盾の原因を取り除くためには、システムのなんらかの部分の寸法、材質、要素相互の配置を変えるだけで十分な場合がいくらでもある。その典型的な例は、エキステンションジブ付きのコールカッターである。ジブはコールカッターの炭層切削部分だが、標準型のジブの長さは2mである。この場合、石炭の破砕は爆薬を使って行われる。地質条件がととのっている場合には、長さ3〜5mのジブを装着したコールカッターを使うことができる。すかし(炭層への切込み)の深さを増すと、コールカッターの動きによって石炭を崩落させることができる。石炭は落下しながら砕け、搬送に適した寸法の大きい破片となる。こうして、量的変化(ジブの長さの増加)が、新たな質的効果(発破作業が不要となる)を生じさせることになる。
次に、問題を解決する新しい方法の中で相当大きな部分を占めるのは、外部環境の何かを変化させるアプローチである。この種の変更が妥当か否かを検討する際は、当該のシステムにとっての外部環境をシステムにどのような影響を与えているかを含めて明らかにしなくてはならない。特に、環境の特性(例えば圧力、温度、運動速度)を変化させることが可能か、あるいは環境をより好都合な特性を持つ別の環境に替えることが可能かを検討しなくてはならない。ある環境から別の環境へと単に置き換えること、あるいは環境に追加の構成要素を導入することによって課題が首尾良く解決される場合もまれではない。例えば、通常のコンクリートミキサーでコンクリートをつくる場合、長時間ミキシングを行ってもコンクリートの中に微細な空気泡が大量に残り、これがコンクリートの強度を低下させてしまう。このために、いわゆる真空コンクリート・ミキシング法が考案された。真空コンクリート・ミキシングでは、ドラム内部を低真空にしてミキシングを行う。環境の持つ様々な特性のうちの1つ(空気圧)を量的に変化させることによって、新たな質的効果(コンクリートの強度が倍加する)が得られる例である。
技術的矛盾は第3に隣接するシステム、同一装置の内部の関連する部品、あるいは工程の別のステップで何らかを変化させる方法によって取り除くことが可能な場合がある。時には、これまで無関係だった別々の工程を何らかの形で結びつけるだけで十分な場合もある。例えば、映画スタジオの照明には主に直流電流が使われる。これは、映画のコマ送り速度(2秒間に24コマ)と交流周波数(1秒間に50サイクル)とが一致しないことに関連している。照明の電源を交流電流にすると撮影カメラのレンズのシャッター開放の瞬間が照明の照度が最小のタイミングに重なることがあり、その結果一部のコマが暗くなってしまう。各コマの撮影時の露出時間は通常1000分の1秒なので直流による照明の場合は光エネルギーのうち有効に利用される率はわずか2.4%にすぎない計算になる。瞬間照明器具を使ってシャッターが開くタイミングに同期させた電流パルスを流せばレンズが開放されている瞬間にのみ照明がオンとなる。人の目は1秒当たりのパルスが10〜16回で連続した光と知覚するので、俳優は弱い照明がずっとついているように感じることになる。映画カメラの動作と照明システムの動作との間にこのように連関させることによって新たな技術的効果(電力消費が大幅に節約され、かつ、俳優も強い照明にさらされないので楽になる)が生まれる。
技術的創造プロセスでは分析段階の作業はほぼ常に単一の結果に導くが、操作段階ではそのようなことはない。1つの技術的矛盾を異なる様々な方法で取り除くことが可能である。それ故、操作段階においては、実験は副次的ではなく中心的役割を演じるようになる。あれこれの方法、手段、スキーム等の中から最適のものを選択する上で実験が決め手となる場合が多い。
操作段階を成功裏に遂行することに不可欠な資質は、自然に関する豊かな知識、観察力、隣接技術分野に関する知見、実験技法を駆使し得る能力である。
(総合段階)
技術的創造プロセスの最終段階である総合段階には4つのステップが含まれる。第1はシステムの変化から必然的に帰結する付随的変更の導入、第2はシステムの変化に必然的に伴う使用方法の変更、第3は原理を他の技術課題の解決に応用する可能性の検討、第4は発明(得られた解決策)の評価である。分析段階と同様、総合段階は主として論理的な判断の積み重ねから成るが、必要に応じて判断の妥当性を実験によって検証する。
技術的矛盾を取り除く方法を発見すると、ほとんど常に、システムに何らかの追加的な変更を加えることが必要となる。この変更の目的は、内容が変化したことに伴ってシステムに新しい形式を与えることにある。しかし、こうした新たな形式への切り替えは心理的に極めて大きな困難をともなう。その理由は、既存のシステム(装置、機構、工程)が人の意識の中で何らかの古い親しみのある特定の形式と結びついているためである。このため、システムの本質が変化しても旧来の「伝統的」な形式が維持される場合がしばしばある。例えば、初期の電動機のなかには蒸気機関と全く同じ形式をもったものがあった。蒸気機関のシリンダーが電磁コイルに、ピストンが鉄心に置き換わっただけで、電流を切り換えると鉄心が往復運動を行い、次に、蒸気機関の場合と同様、クランクとピストンロッドの機構によってこの運動が回転運動に変換されるというものだった。クランクを不要とする回転子を持ったモーターが創られたのは、それよりも後のことである。
総合段階の次のステップは、システムの使い方を変化させることである。あらゆる新システム(あるいは既存システムの改良)はその新規性に対応する新しい使い方を発見することを求める。今では古典的となっている1つの例をあげよう。坑内掘の採炭夫は従来つるはしを使って手作業で石炭を破砕していた。採炭夫はある程度掘削すると破砕作業を停止して、支保(掘進した坑道を支柱で補強する)作業を行っていた。1930年代初頭になると炭鉱に空気式ピックハンマーという強力な石炭破砕装置が出現した。しかし、作業方法は従来のままで、採炭夫は相変わらず定期的にハンマーをわきに置いて支保作業を行っていた。こうした不合理な作業手順となっていたため、ピックハンマーを導入しても全体の生産性はわずかしか向上しなかった。そこで、1グループの採炭夫が連続的にピックハンマーによる作業を進め、別のグループが専門的に支保作業に従事するという、新たな作業体制が考え出された。こうすることによって漸くピックハンマーの高い生産性を活かすことが可能になり、採炭量は何十倍にも増加することになったのである。
このステップの重要性は明らかだが、技術者は往々にしてこれにしかるべき注意を払わず、結果として新発明を最適に活かす方法は生産管理部門が試行錯誤を通じて発見するのに任せることになっている。直前のステップの場合と同様に、旧来の伝統的な作業方式が技術者の心理に影響を与えるためである。
総合段階の第3ステップは、技術的矛盾をとりのぞく新しい方法を他の技術課題の解決に応用することを検討することである。操作段階で発見された矛盾を解決する方法の原理は個々の具体的な発明よりも大きな価値をもっていて、より重要な別の課題を解決するために活用できる場合もある。このステップでは、技術者の視野の広さ、他の技術分野に関する知見、様々な産業部門がかかえる現実的な問題についての知識が特に重要な意味をもつ。
公知のことだが、鉄筋コンクリートに関する最初の特許は1867年にフランスの庭師モニエによって取得された。しかし、モニエは十分な技術的視野を備えていなかったので「鉄筋コンクリート製の植木用の鉢の製造」に関する特許しか取得しなかったのである。
技術的創造プロセスの最終ステップは、行われた発明を評価することである。このステップの目的は発明によって得られるプラスの効果と発明を実地に移すために必要な費用との相関関係を明らかにすることである。発明の価値はこの比率によって決まる。特に、操作段階で得られた解決案が複数存在する場合には、最適の案を選択する判断はこの評価に基づいて行われる。通常このステップではここまでやってきた作業をふりかえる分析作業を行い作業過程での誤りを明らかにし、また課題の解決に利用した新たな創造的方法の意義を考察する。
(まとめ)
ここで例を挙げて技術的創造の全プロセスの流れを説明する。1949年にソ連邦石炭産業省は、地下(坑内)火災の際に高温有毒ガスの中で消火活動に従事する鉱山保安要員のための保冷服の開発をテーマに全国発明コンクールを行った。コンクールの課題の保冷服に対する技術要求の要点は長時間にわたって保冷能力を保持し続けかつ重量を8〜10kg以内におさめるというものだった。重量の条件が付けられたのは、鉱山保安要員は作業時に呼吸装置(12〜14kg)を装備した上に消火器具を持たなければならず、一方で人が身につけて動ける重量の許容限度が28〜29kgとされたためである。
本論文の筆者は、次の基本的な技術的矛盾を特定するところから始めて保冷服の開発に取り組んだ。すなわち、保冷服の冷却作用の持続時間を十分なものとするには冷却材(氷、ドライアイス、フロン等)の量を多くせざるをえず、したがって保冷服の重量を増加させることが求められる。逆に保冷服を軽量化しようとすると、冷却時間を短くせざるを得ない。このように、2つの基本特性(重量と冷却時間)の間には通常の方法では解決不能な矛盾が存在している。矛盾をこのように分析した結果、課題の難しさの原因はコンクールによって設定された重量の限度が低いことであることが明らかになった。
この種の矛盾を取り除く方法について研究したところ、他の技術分野においてはこれを解決するためにしばしばいわゆる「複数機能兼備法」が使われていることが明らかになった。これは、あるシステムに他のシステムの機能も併せて受け持たせることによって2つめのシステムを省略して、その分始めのシステムの重量を増加させるという考え方である。本件の場合は、保冷服に呼吸装置の機能も分担させれば課題を解決できる。こうすることで、組合せ式の保冷服の許容総重量を20〜24kgまで引き上げられることになる。問題をこのように設定すると冷却材の選択肢も絞り込まれる。すなわち冷却材として使えるものは液体酸素以外にない。酸が気化し温度が高まる際に保冷服の内側が冷却される、こうして暖められた酸素は呼吸に使用される。
総合段階では、解決策から必然的に帰結する変更がシステムに加えられた。酸素備蓄量を増やすことができるので、循環型(再生式)呼吸システムを止めて開放型システム(呼気を大気中に排出する)に変更した。この変更によって保冷服の呼吸装置の構造を大幅に単純化することが可能となる。さらに、保冷服の使用方法にも変更が加えられた。作業の過程で気化した酸素は呼吸後排出されるのだから、保冷服の重量は次第に軽くなる。これを考えに入れれば、保冷装置の液体酸素の量は最初は多めにしておくことができる。これによって保冷服の冷却継続時間をさらに増加させることが可能になった。
このようにして発見された複数の原理を採用した保冷服の設計は審査員によって1等、2等の2つの賞を与えられた [3]。
以上説明した技術的創造プロセスの骨子は次の通りである。
- 分析段階
- 課題の選択
- 課題中の最重点の抽出
- 進化を制約している矛盾の発見
- 矛盾の直接原因の確定
- 操作段階
- 典型的解決法(モデル)の研究
- 自然のモデル
- 他の技術分野のモデル
- 解決策をもたらす新しい方法を、次の各部分を変更する観点から発見しようとする探索
- システムの範囲内
- 外部環境
- 隣接システム
- 典型的解決法(モデル)の研究
- 総合段階
- システムの変化から必然的に帰結する付随的変更の導入
- システムの変化に必然的に伴う使用方法の変更
- 原理を他の技術課題の解決に応用する可能性の検討
- 発明の評価
我々が上に輪郭を示したスキームは、経験を積んだ高度に熟練した技術者がおこなう創造的活動についてのみ当てはまるという点を指摘しておく必要がある。かけだしの技術者が革新的な結果を得るケースでは、個々の判断に十分論理的な整合性が無く、偶然、まぐれ当たり等々が大きな役割を果たしている。これと逆に、過去の偉大な発明家は高水準の創造技能に達していた場合が多い。
発明は科学的研究の過程で生まれることもある。例えば、エックス線の発見とその特性の解明によって、ほとんど自動的にエックス線を利用する一連の技術的発明が生まれた。この場合には、多数の技術的矛盾を除去するための手段が発明者の掌中に最初から存在し、逆に、その矛盾を発見することが課題となった。
我々が示したスキームは典型的スキームであって、すべてを包括するスキームではない。それだけでなく、このスキームは、その適用可能性の範囲内にあってさえも、近似的な妥当性をもつに過ぎない。このスキームは、多くの点で更なる明確化と掘り下げを必要としており、またいくつかの点では修正が必要となることだろう。
こうした問題点を克服するためには、技術の進化の客観的法則と技術的創造の心理過程との間の相互連関について一層の研究を行わなければならない。さらに、開発、生産技術分野の技術者の経験を体系的に研究し、創造的な仕事に共通する方法を解明し、一般化する必要がある。
心理学の一部門としての発明的創造の心理学を確立するには、実験的方法を幅広く適用することが不可欠である。研究で得られた結論は、古い発明に関する資料に照らして検証するだけでなく、実験的手法によっても検証を行う必要がある。なぜなら、実践こそが発明的創造の心理学の最終目的であるからである。こうして明らかにされた法則性は、発明という行為についての科学的方法論の開発に利用されなければならない。
引用文献
- K.マルクス『資本論』第1巻 (Маркс К. Капитал, т.1.)
- K.G.ヴォブルイ『科学研究者の労働の組織化』第三版、1948年 (Воблый К.Г. Организация труда научного работника. — Уфа, 1943; 3 изд., Киев, 1948.)
- 「坑内掘炭鉱内における高温下での鉱山保安作業」、石炭技術出版所、1951年、32頁 («Горноспасательные работы в шахтах при высоких температурах». Углетехиздат, 1951. — 32с.)
- カルネツキー編『一般熱工学』1952年 (Общая теплотехника. под ред. Карнецкого, 1952.)
- T.リボー『創造的想像力』1901年 (Рибо Т. Творческое воображение. — С.-Петербург: Типография Ю. Н., 1901. — 329с.)
- S.L.ルビンシュテイン『一般心理学概論』第二版、1946年 (Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. 2 изд. 1946.)
- P.M.ヤコブソン『発明における創造的活動のプロセス』1939年 (Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя. — М.-Л., 1939.)
- Rossman, J. Psychology of the inventor. Washington D.C.: Inventors Publishing, 1931.
G.S.アルトシューラ、R.B.シャピロ「発明的創造の心理学について」
雑誌『心理学の諸問題』第6号
1956年、pp.37-49
(Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б.
О психологии изобретательского творчества
// Вопросы психологии. — 1956. — № 6. — с. 37-49.)